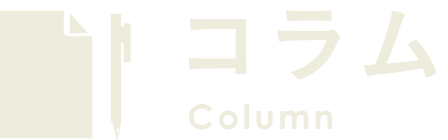

2025年5月28日
(公財)流通経済研究所 事業・研究統括 兼 デジタル・サービス部門長
主席研究員 折笠 俊輔
スーパーで販売される米の平均価格が4,285円/5kgとなり、過去最高値を更新した今、米価の高騰が世間で大きな話題となっている。
政府は米価高騰への対策として緊急事態用に政府が保管している備蓄米の放出を決定し、2025年3月には競争入札方式で集荷業者への売り渡しを行った。しかし、5月になっても放出した備蓄米は小売店頭の販売に回らず、米価は高止まりしている。その状況下で大臣が交代し、米価の高止まりに危機感を覚えた政府は競争入札ではなく、随意契約で小売業に直接、備蓄米を放出する方向に施策の転換を行った。随意契約による販売価格は約1万1千円/俵とし、5kgあたり2,000円前後の店頭販売価格を目指している。
この随意契約による備蓄米の施策は、米の流通・販売という面では大きく2つの意味合いを持つ。
ひとつは、消費者に対し「選択肢を提供できる」という点である。令和6年産の一般銘柄米は4,500円前後/5kg~となっているなか、備蓄米はその半額の2,000円/5kgであるが、令和4年産、いわゆる古古米である。そして、競争入札で放出された備蓄米も同時に店頭にならぶとすれば、3,500円前後/5kgの令和6年産・5年産のブレンド米である。松竹梅のように大きく米に3つの価格帯ができることになる。2,000円は安すぎるといった声もあるが、消費者の視点に立てば選択肢が生まれることになり、自分のライフスタイルに合わせた米を買えるメリットがある。節約志向が強ければ2,000円の備蓄米を、米の味にこだわるなら、銘柄米を購入することができる。こうした状況が生まれることは政府の目標としている「コメ離れ」を防ぐ意味では一定の効果があるだろう。
もうひとつは、小売業が玄米を直接購入して、店頭に並べることができるかどうか、といった今まで試したことのない米の流通ルートへの挑戦という意味である。今までは、精米や袋詰め、細かい配送などは全て卸が担ってきた米のサプライチェーンにおいて、小売業が米を買い、委託で精米などを行い、販売するといった流れは全く新しいものであり、今回の備蓄米販売の結果によっては、米のサプライチェーンにおける所有権の移転を含めた商流・物流のあり方が変わるキッカケになる可能性がある。
しかし、この備蓄米の放出は対処療法的なものである。根治を目指すのであれば、問題の本質を解決しなければならない。今回の米価高騰の根本的な要因、つまり問題の本質は生産量が元々足りていないことにあるだろう。
2024年の米の需要量は農水省の統計で705万トンであった。これは当初の予測であった690万トンよりも15万トン多い。農水省の米の需要量の推計は、日本の人口×1人あたりの消費量の平均で算出されている。2025年の需要量が当初の推計よりも多くなった理由は、南海トラフ地震警報があったことによる家庭備蓄の増加と、インバウンド需要の高まりによるものと考えられるが、需要量の推計にこうした要素が入っていないのである。
では、2025年(令和6年産米)の当初の需要量の見込みはどうだったか。674万トンである。前年、705万トンの需要があり、インバウンド需要も続き、万博も開催されているなか、本当に30万トンも米の需要は減るのであろうか。おそらく減ってはいないだろう。700万トン程度の需要はあるはずだ。
そして、この需要量の推計に基づき、生産調整が行われている。674万トンの需要に合わせた生産調整が行われ、計画通りの生産がなされた場合、作況指数は100を超えていても、30万トン程度の米が不足する。また、実際に足りていないという状況だけではなく、生産量、需要量の統計が全て推計であることから、正確な不足量が分からないことも市場のコメ不足感を加速している。
今回の米価の高騰は、「米の需給バランスが崩れ、供給が不足すると大きく価格が跳ね上がり、消費者の家計を圧迫する」ということを明らかにした。一方で、「米の需給バランスが崩れ、供給が過多になると大きく米価が低下し、生産者の経営を圧迫する」ということも過去の事例で既知である。需給バランスをどう考えていくべきなのだろうか。
米は日本の国民の食生活の基礎であり、最も重要な主食である。食料安全保障を考える上でも最重要な品目である。自国で国民が飢えない量を供給できなければならない。
備蓄米によって、当面の米価高騰対策をすすめる一方で、今回のような事態を引き起こさないための新たな施策が必要であろう。需給バランスを調整するために供給側を抑制する施策(生産を減らす施策)を続けてきたが、米価を下げ、安定させていたくためには供給を増やす、つまりは増産する施策が必要である。需給バランスの調整は、需要側を調整することが望ましい。具体的には供給量が多い場合、輸出に力を入れるなどの施策が考えられる。
他にも、生産者への直接支払制度や、備蓄米の量の積み増しなども考えられる。今こそ、今後の日本のコメ政策をどのようにするのか、減産から増産への政策転換を含め、中長期的な戦略が求められている。