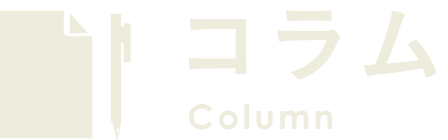

2025年7月23日
(公財)流通経済研究所 常務理事
主席研究員(事業・研究統括)折笠 俊輔
ある地域に2店舗だけある食品スーパーと、全国に数百の店を持つ大手食品スーパーチェーンがあったとしよう。一般的に、地域密着の小型スーパーの方が地域密着の営業ができるため、その特定の地域では強みを発揮する、と言われる。つまり、このケースでは2店舗だけの食品スーパーの方が、大手チェーンよりも地域密着型の経営ができるということになる。
はたしてそれは本当だろうか?
当然、2店舗の食品スーパーの方が地元の人の好みを長年の営業経験で知っているかもしれないし、地元の店とて愛されている可能性はある。また、何かの打ち手を考える際には、店舗数も少ないため、より迅速に実施できるだろう。そういった意味で、小型スーパーの方が地域密着といえるかもしれない。
しかしながら、大手チェーンの方が地域の特徴を把握し、対応することができている可能性もある。それは「比較」ができるためである。全国に数百の店を持つ大手チェーンであれば、地域ごとに消費者がどのような商品を好むのか、あるいはどういった時期にどういった購買行動をとるのかを、他の地域との比較で把握することができるのである。地域間の比較を行うことで特定の地域の特徴を、より詳細に記述できる。地域への理解が深まれば、接客や品ぞろえなどで地域に合わせた対応ができるようになり、競争力が増す。さらに大手の資本力があれば地域ごとに合わせたマーケティングや店頭マーチャンダイジングも、フットワーク軽く実施できる可能性もある。
これは食品スーパーに限った話ではなく、農業経営の分野においても同じことが言える。「海外の企業や大手企業は、うちの地域を知らない」、「この地域で長年やってきた自分が一番、地域のことを理解している」と漠然と思っていると危険である。大手企業や海外の企業は、他の多くの地域における実績とデータを持っており、それらを活用することで地域の理解度を科学的に深めることができるのだ。そして、それらに合わせた対応も、大きな資本力を背景に実施できるのである。
「井の中の蛙、大海を知らず」という諺がある。これは、自分の持っている狭い見識にとらわれてしまっている浅はかさを、大きな海を知らない井戸の中の蛙に例えたものである。
地域の中で生きる農業者、農業経営者、農業関係者ほど、外の世界を知る必要がある。他の地域では、どのような課題に対し、どのような対策を取っているのか、世界ではどのような技術が、どういった形で用いられているのかなど、自分の作目や地域とは直接関係しない情報にも触れ、その背景も含めて理解することが自分の農業や地域を考える上で重要である。他の地域と比較した自分の地域の理解と、世界の動向を理解した上での打ち手や取り組みができるような視野を得ることができるからだ。
大海を見て、大海を知った上で、自分の住まう井戸を客観的に分析し、課題を明確化したうえで、大海の動向も踏まえた改善を行う蛙こそ、最後まで生き残る蛙なのだと思う。