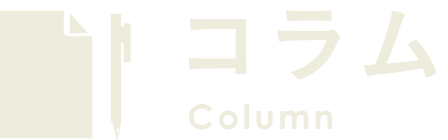

2025年9月26日
(公財)流通経済研究所 常務理事
主席研究員(事業・研究統括)折笠 俊輔
「風が吹けば桶屋が儲かる」という言葉がある。これは、一見関係のない出来事が連鎖して大きな影響を及ぼす様子を表している。しかし、昨今の農業経営においては、世界情勢が自分の農業経営に影響を及ぼすことが増えてきた。
例えば、ウクライナとロシアの戦争は、ウクライナからの小麦の輸出が減少したことで世界の小麦価格が高騰し、それが日本でも小麦のみならず、小麦商品の需要減をもたらし、米の消費量を増加させたことで米価格高騰に影響をもたらした。さらに、ウクライナ戦争はリンやカリウムの供給も減少させたことから、肥料価格高騰にも影響したと言われている。
中東の情勢がガソリンや軽油価格に影響し、世界的なSDGsの動きが、日本の農業政策に影響し、細かい部分ではビニール製のマルチの需要を減らしたりしている。情報伝達がインターネットで円滑に進むようになり、エネルギー供給などを中心にサプライチェーンが世界的な規模で構築されている今では、一見、遠いところにあるように見える世界の動向が自社の経営に影響してくることは一般的なものとなった。風が吹けば桶屋だけではなく農家が儲かるかもしれないし、損をするかもしれない時代であると言える。
農業経営において、最も重要な要素の一つに「地域との関係性」や、「自分の圃場の土壌の理解」、「地域特性の把握」がある。環境を利用した産業であるが故に、農業経営においては地域密着が求められる。それは今までも、これからも間違いなく重要なものである。地元・地域こそが農業という産業の土台にあるからだ。
しかしながら、これからの農業経営においては、地域だけに目を向けているわけにはいかない。遠い異国の戦争が自社の生産コストや販売に大きく影響する時代なのである。さらに言えば、海外の農業支援アプリケーションが日本でも大きく展開されている。そして政府は農産物の海外輸出を政策の1つの柱に置いている。もはや自分の農業経営を考える上で「世界」は切り離せないものとなった。
今こそ農業経営者は世界を見るべきだ。海外の先進的な農業者の視察や、最新技術の把握、世界的な企業経営のあり方について学ぶことが重要である。今では、海外農業研修が様々な団体で用意されていたり、日本国内の展示会でも海外の農業関係企業が出店していたりする。また、ドイツでは2年に1回、アグリテクニカという世界最大の農業技術の見本市が開かれているし、フランスで2年に1回、SIAL Parisという世界最大規模の食品見本市が開かれる。アメリカでもワールドAGエキスポという農業の展示会が大規模に行われる。
世界という森を見て、そのうえで自分の地域という木を見ることで新たに見えるものは多いだろう。外務省によると日本人のパスポート保有率は17%(2024年)ということである。およそ6人に1人しかパスポートを持っていない、つまり海外に行っていないことになる。日本国内でも一定の情報は取得できる状況ではあるが、現地に行って、現地の人々とコミュニケーションを取り、自分で見聞きして初めて見えることもある。
繰り返そう。今こそ、農業経営者は世界を見るべきだ。