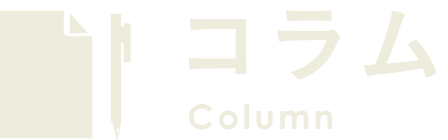

2025年10月27日
(公財)流通経済研究所 常務理事
主席研究員(事業・研究統括)折笠 俊輔
高市政権の誕生に伴い、農林水産大臣が小泉氏から、鈴木憲和氏になった。就任後の会見では、「コメについては需要に応じた生産」にする旨と、「価格への介入を行わない(米価高騰時に備蓄米放出等を行わない)」旨が発表された。これは備蓄米を通じて積極的に価格への介入を行い、増産を閣議決定した前大臣の方針からの転換とも言えるだろう。
なお、令和8年のコメの生産量の目標も約711万トンと発表された。これは令和7年産のコメの生産量の見込み748万トンから減少する目標であり、概ね令和6~7年の需要量と一致する。この背景には、令和7年産米が、期末の在庫量も適正水準を大きく超えると見込まれていることがある。このまま令和8年もさらなる増産を行った場合、「コメ余り」によって価格が暴落するリスクが高まることから、需要に合わせた「増産」から「生産」へ舵を切ったと考えられる。
これは、コメ価格高騰対策として生産者側のリスクを低くするための方針転換と捉えることができる。よって消費者側を見てきた前大臣と比較すると、新大臣は、より生産者側を見ているとも言える。
増産ありき、ではなく需要に応じて生産する、という方針への転換は、いわば「令和5年くらいまでの施策に戻す」という意味でもある。よって、以下の2点が大きな課題となるだろう。
ひとつは、需要量と生産量(供給量)の適切な把握である。結局、需要量・生産量を見誤ると、需給バランスが崩れ、大きな米価の高騰や暴落を引き起こす可能性がある。需要量の予測と生産量の把握を、今まで以上に精緻に実施していく必要がある。
もう一つは、需要拡大施策への注力である。需要が減少するから、生産量も絞っていく方法では、長期的に見た場合、コメ産業の衰退にしかつながらない。産業の成長を考える上では、需要を拡大し、増産していくようにしなければならない。そのためには輸出の需要もそうだが、国内需要についても、さらに喚起していく必要があるだろう。今回のコメ騒動で消費者のコメへの理解が進んだこともある。国民1人あたりの年間消費量を拡大するような施策も期待される。
今回、政府のコメ政策は、増産と発表して2ヶ月程度で、その方針が撤回された。農業経営としては、政府の動きや補助金などは非常に重要であるものの、政局や大臣交代などに振り回されないようにしていきたいものである。そのためには、「①単収を上げること」、「②生産コストをおさえること」、「③自分で価格を付けて販売すること」といった基本的な事項の徹底が肝要となる。今後、コメ価格(概算金も含めた玄米の生産者からの買取価格)は、今年よりは下がりつつも、1俵2万円代の相場となることが見込まれる。2万円~/俵が維持されるのであれば、どういったコストで、どういったコメを作り、誰にいくらで販売していけば、政策に左右されない(補助金に頼らない)稲作経営ができるのかを考えることができるだろう。政府による補助金を使った需給調整も継続されると思われるが、コメ騒動の後は、補助金が無くても成り立つ経営を意識していきたい。