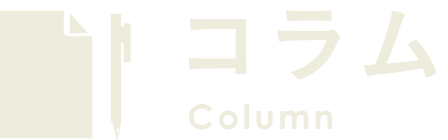

2025年6月26日
(公財)流通経済研究所 農業・地域振興部門
研究員 菅原 彩華
例えば、生産者が自身で生産した農産物を使って加工品の商品開発をしたいと思い立った時、何から始めると良いのだろうか。商品のイメージはできていても、全く未経験の状態から、製造するための原料や包装資材を調達したり、製造事業者(OEM先)を探したりするのは難しい。また、商品が完成してもその販売場所を確保して、継続して販売していく仕組みづくりも簡単にはできない。
良く聞く話で、「この規格外品の使い道ないかな…」という生産者の悩みに対して、「6次産業化したら良いじゃない!」という答えは、簡単に答えが出ているようにも見えるが、現実問題としては実現性に乏しいケースが多い。6次産業化をはじめとして、「新しいビジネスを作る」ということは、継続して事業を続けていける状態までもっていく道のりが長く険しく、1人で実現するには多くの労力と時間が必要となる。
そのような時は、地域内外の様々な事業者との連携を考えたい。餅は餅屋。1次~3次事業者でそれぞれの工程を分担し、商品を開発、製造、販売することで効率良く商品開発・製造・販売ができる。生産者1人ではなく地域全体で取り組むことで、効率よくビジネスが作れる。では、どうやって連携できる事業者を探せばよいのだろうか。県に相談したら良いのか、市町村に相談したら良いのか、仲間の生産者に繋がりのある事業者を聞いてみたら良いのか。どうしたら良いか、頭の中では分かっていても行動することが難しい生産者もいるだろう。
農林水産省では、令和3年度~令和6年度の4年間、「地域食品産業連携プロジェクト(LFP)推進事業」(以降、LFP)を実施していた。(過去のコラムでも取り上げている)これは地域の社会課題を解決するビジネスを地域が連携して創出することを支援する事業であった。例えば、未利用資源(規格外品や製造の過程で廃棄される原料等)を活用した商品・サービスの開発を促進し、経済性との両立を目指す、というような取り組みである。地域内外の1次~3次事業者がネットワークに参画し、その繋がりを活用して商品やサービスの開発を目指していくこの事業では、各道府県で事務局を整備し、事業者の活動をサポートする。今回は、このLFP事業の事例から活用できるポイントを考えたい。
農林水産省ウェブサイトによれば、このLFP事業では、過去4年間の実施で33道府県が参加し、150を超えるビジネス(商品やサービスの開発)が生まれたという。また、今年度は、LFPを拡大させた後続事業がスタートしている。後続事業では、川上・川中・川下にとどまらず消費者も一体となって、食料システムの構築に向けて持続可能な取り組みとして実施していくことが求められており、これまで以上の事業者間の繋がりや継続性といった部分が重要とされている。
これまでは地域内または都道府県内における同じ業種の事業者との繋がりは業界団体等で構築しているケースが多かったが、業種の枠を越えた繋がりを設けられる場は、なかなか存在していない。また、都道府県によっては、同じ都道府県内でも地域(エリア)間のネットワークが弱いところも少なくない。業種やエリアを超えたネットワークの構築にとって最も効果的な方法は、「商品開発」などの新規ビジネスを創出するという同じ目標に向かって取り組むことである。
ここで山形県のLFPの事例を紹介しよう。山形県は、4つの地域に分かれており、特に海に面する地域と内陸に位置する地域とでは、中々繋がりを作ることができていなかった。そこで、山形県とLFP事務局(弊所)は、研修会や事業構築の会議といった地域や業種を越えた参加者が集まる機会(意見交換会や名刺交換会)を創出し、やまがたLFPのネットワークを活用してもらうことをとことん促した。結果、名刺交換を目的とした事業者の参加もあり、地域や業種の垣根を越えた情報交換や関係性構築が実現できた。この関係性の中で、搾汁後のラフランス残差を活用した発泡酒や、鶏節を使ったアートパスタの開発・商品化を実施することができた。
山形県の取組では、予想外の反応もあった。研修会や戦略会議の周知をチラシやウェブサイト、SNS等からしていたが、山形県や事務局の手が届かなかった業種・地域からの参加申込やネットワークへの参画があった。これは後から分かったことだが、やまがたLFPのネットワークに参画し、そのなかで商品開発をしていた事業者が周知も兼ねて様々な場所で、内容を紹介していたことが、ネットワークへの参画のきっかけとなったのだ。なお、LFP事業において、商品開発を実施した事業者は、開発途中や完成後にLFP事業のネットワークを使い、バイヤーと意見交換を実施し、バイヤーとの繋がりも深めることもできた。
つまるところ、新たなビジネスを地域を巻き込んで生産者が立ち上げるとき、自社や既存のネットワークだけで実施が難しい場合は、地域や業種の垣根を越えたネットワークを構築することが重要であると言える。こうしたネットワークとそれを通じた取り組みは、地域の刺激となり、次年度以降の取組に繋がるだろう。

開発後の商品を発表する様子
現在は自治体などが、地域や業種の垣根を超えたネットワーク構築を推進していることで、事業者同士が繋がる機会や場所を生み出している。しかしながら、各地域の抱える課題や、事業者の課題は多種多様であり、同じ課題と目標を持った事業者が偶然に出会うことは難しい。そのため、地域内で事業者をつなぐネットワークを構築できる受け皿やコーディネーターが重要となる。コーディネーターとしては、例えば地域の商工会議所や観光物産協会などが考えられる。コーディネーターが能動的に地域や業種を超えた繋がりの構築を支援し、地域全体で団体戦として地域課題の解決に取り組んでいくことが非常に重要であると言える。地域の団結力と底力、そして行動力を全国の事業者に期待したい。